top of page


ハイイロゲンゴロウ
池の氷の中で越冬 凍ってもなお生きる 寒さが厳しいこの季節、池の水をのぞいてみると、水面に張った氷の中に越冬する虫を発見できるかもしれません。 「ハイイロゲンゴロウ」もそのうちの一つです。日本全国に生息していて、最もよく見られるゲンゴロウの種類です。池や沼のほか、水たまりや...


ミノムシの越冬
外の寒さ通しにくく厚くて頑丈な「蓑」の巣 葉っぱがほとんどなくなった木にぶら下がっているミノムシ。この時季の風物詩ともいえるおなじみの光景ですが、実はミノムシは、自治体によっては絶滅危惧種にも指定されるほど貴重な昆虫になってきています。...


サカダチゴミムシダマシ
わずかな水分求めて 砂漠で霧の朝「逆立ち」 世界には100万を超える種類の虫がいて、中にはアフリカの砂漠に生息しているものもいます。 極端な暑さや寒さ、乾燥といった、過酷な砂漠地帯で生きているのが「サカダチゴミムシダマシ」です。この虫は生きていくために必要な「水」を、ある方...


カブトムシの冬支度
秋に急成長する幼虫 北と南で異なる適応 信州ではあっという間に終わってしまう過ごしやすい季節、足元では虫たちも冬に向けて大急ぎで準備をしています。 たとえば「カブトムシ」の場合、夏の終わりに卵を産み、今は幼虫が大きくなる時期です。卵からかえった時は1センチにも満たないほどの...


台風で巣が壊れたハチ
草の茎に巣を修復 失敗繰り返さぬよう 台風が最も多くやってくる今の時期、人間以上に翻弄(ほんろう)されるのが「虫」です。強い雨や風によって、家である「巣」が壊されてしまうこともあります。 もし巣がなくなってしまったら、虫はどのような行動を取るのでしょうか。巣を丁寧に修復した...


トンボのはね
空気の渦つくる表面 強風の空もすいすい 強風でセミが飛ばされているのを目撃しました。さらに驚いたのが、トンボは風をものともせずにすいすいと飛び回っていたことです。 この違いはどうやら「翅(はね)」にあるようです。トンボの翅は、表面がでこぼこしていて、翅に前から風が当たると、...


天気と関係 セミの羽化
晴れた日の暗い時間 地中から様子を観測 夏本番を知らせるように、セミが鳴き始めました。 セミは一生の大半を土の中で幼虫として過ごします。ようやく外に出て成虫になっても、そこから1〜2週間しか生きられず、短い命を燃やすように一生懸命鳴くのです。...


カタツムリと梅雨
貝の仲間 乾燥が苦手 湿度高いと活動的に 最近カタツムリをよく見かけます。そこでふと気が付いたのが、カタツムリは梅雨の時期以外はあまり姿を現さないということです。なぜなのか調べてみました。 カタツムリは貝の仲間で、もともと海で暮らしていたため乾燥が苦手です。活動的になるの...


うるさい季節
最も過ごしやすくて ハエが「五月蠅い」6月 一年で最も過ごしやすい時季を迎えています。気温によって行動が左右される虫たちが元気に動き回る季節でもあります。 しかし、元気すぎるがゆえに不名誉なかたちで言葉の由来になった虫がいます。...


クモの雨ポーズ
垂直に垂れ下がり 雨粒の衝撃避ける 雨の日は「クモの巣」をよく見かけると思ったことがありませんか。これはクモの巣が雨の日に増えるのではなく、雨粒がついてキラキラ光ることで見つけやすくなるためです。 運が良いと、「クモの雨ポーズ」を見られるかもしれません。...


アメンボの引っ越し
冷たい風吹く水面から 落ち葉の下や土の中へ 春本番を迎え、冬の間それぞれの場所で寒さをしのいでいた虫たちも、元の場所に戻り始めています。 アメンボもその一つです。田んぼや池にいるイメージが強いアメンボですが、冬は水辺から離れて過ごします。...


チョウの目覚め
「発育零点」を基準に 温度差で「春」感じる 「蠢く」—この漢字の読み方、ご存知でしょうか。「うごめく」と読みます。よく見ると、春の下に虫が二つ付いていて、春になり土の中から虫がモゾモゾ出てくる様子を漢字一字でよく表しています。...


寒さに弱いカメムシ
暖かい民家に移動 白い物に集まる習性 一年で最も寒い時期を迎えています。虫たちもそれぞれの方法で寒さを乗り越えていますが、成虫で越冬するものは、涙ぐましい努力をしています。 例えば、カメムシは成虫の姿で冬を越すというのに、残念なことに寒さにめっぽう弱いそうです。ある程度の寒...


水中で越冬する虫
表面の水が凍っても 池の中は4度のまま 冬は昆虫にとっても寒くて厳しい季節です。凍え死んだりしないよう、安全な場所を選んで冬を越しています。 例えば、トンボは、秋に卵を産むものが多く、冬の間は卵や幼虫の姿で、池や田んぼの用水路などの「水の中」で過ごします。種類によっては何年...


カマキリの冬越し
泡に包まれた「卵のう」 冬の寒さから卵守る まもなく受験シーズンに入ります。今回の気象予報ムシは中学入試の理科でよく出題される「昆虫の冬越し」の話題です。 昆虫が冬を越す姿には「卵」「幼虫」「サナギ」「成虫」の四つのパターンがあります。...


モンシロチョウの冬眠
「日の長さ」に反応し さなぎの姿で冬へ 人と同じように、小さな虫たちもこの時期はあの手この手で冬支度をします。 アゲハチョウやモンシロチョウは「さなぎ」の姿で冬を越します。冬にチョウの姿になると、寒さや飢えで死んでしまうからです。...
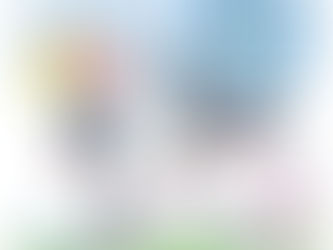

アサギマダラの「渡り」
「暑い」も「寒い」も苦手 何千キロも飛び続ける 2年前の9月下旬、長野市の地附山で「アサギマダラ」を見つけました。 アサギマダラは日本で唯一生息地を移る「渡り」をするチョウです。10センチほどの小さな体で、1000〜2000キロを移動します。夏は涼しさを求めて東北や長野県の...


クマムシと宇宙天気
宇宙環境の変化観測 ひまわり10号に期待 地球上で最も生命力が強いといわれている生き物がいます。それは「クマムシ」です。 クマムシは8本足の体長1ミリにも満たない微生物です。踏みつけたら簡単に死んでしまいます。では何がすごいのか。その実力は体を乾燥させ、体内の代謝を停止させ...


テントウムシの夏眠
草の茂みや葉の裏でじっと 呼吸量は著しく低下 観測史上最速の梅雨明けとなった今年、長い夏にお疲れの人もいると思います。 昆虫にも暑さが苦手なものがいて、中には夏の間「かみん」をする虫もいます。「仮眠」ではなく「夏眠」です。暑さに耐えるため、草の茂みや葉の裏でじっと過ごすので...


雨に強いチョウ
その秘密は羽の鱗粉 驚きの雨を弾く強さ 雨の日は外出が億劫になりますが、昆虫も雨が降ると葉の裏などにじっと身を潜めます。中には雨にぬれても平気な虫もいて、チョウもその一つです。 なぜチョウは雨に強いのか。その秘密は羽についている「鱗粉」にあります。チョウを触ったとき、手に粉...
bottom of page
